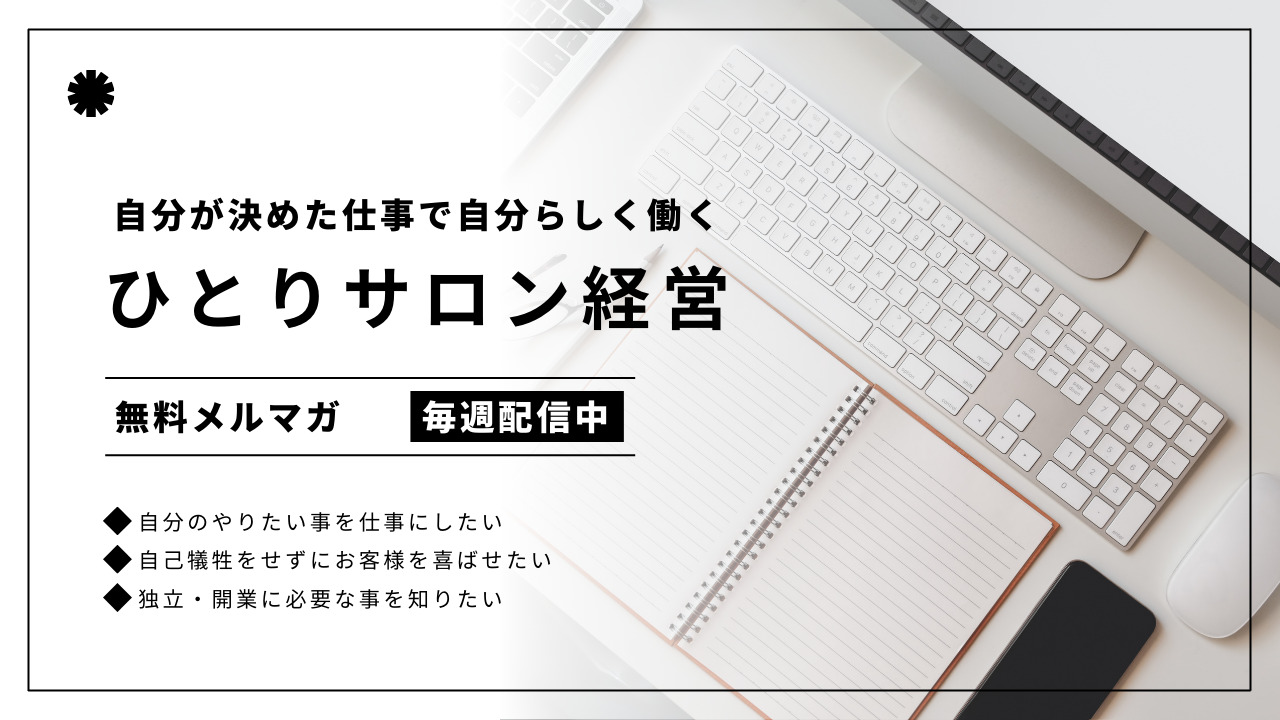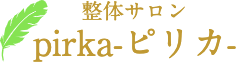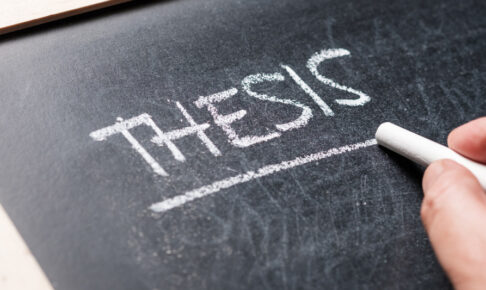こんにちは。整体サロンpirka-ピリカ-の山田です。
頭痛は、現場で最も頻繁に遭遇する症状のひとつであり、単純な頚部筋の緊張やストレスだけでなく、眼(視覚・眼運動系)との深い関連性が近年数多く報告されています。
本記事では、頭痛と目(眼の構造・機能・運動)との関係性に焦点をあて、解剖学・生理学を基に分かりやすく解説し臨床に活かしていただければと思います。
整体師、柔道整復師、理学療法士、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。
目次
頭痛と眼系の“なぜ関係するのか”という基礎論
頭痛が発生するメカニズムは多岐にわたりますが、特に眼との関連が深いとされるものをご紹介します。
①眼からの過剰な視覚入力
視覚系・脳・三叉神経・眼神経などの視覚に関係する構造に過剰な刺激が加わり続けると頭痛誘発条件となります。
例えば、画面凝視・長時間近距離作業・眼精疲労による緊張があげられます。
②眼運動の異常とドライアイ
視覚への刺激によって、中枢神経系および眼‐頸‐頭部筋膜連鎖を介して頭部・頚部の筋や神経、膜構造に影響を及ぼす可能性があります。
視覚への刺激により、頚部や肩部の筋肉が緊張し頭部への虚血を引き起こし、頭痛の原因となるのです。
また眼表面の乾燥(ドライアイ)が、眼の痛み・違和感・過敏性を通じて頭痛(特に片頭痛)の誘因として報告されています。
例えば、大規模コホート研究では片頭痛患者はドライアイを併発する確率が有意に高いという報告があります。
眼から来る頭痛について
これらを総合すると、眼系と関係がある頭痛は
①「視覚・眼運動を通じた入力過多/入力異常」
②「頭部筋膜などの緊張による神経・血管の圧迫と虚血」
によって発生すると考えられます。
臨床的応用:評価・介入・アプローチ方法
評価
では、頭痛に対する実際の臨床ではどのように評価、対応していけば良いかを解説していきます。
もちろん筋筋膜性の頭痛では頚部や肩部の筋緊張が高いので、関係のある筋肉や関節の可動域や硬結、神経症状、疼痛の有無を確認しましょう。
それに加えて、以下の眼のチェックも行うと施術以外でのアドバイスや指導の幅が広がります。
両眼協調(輻輳能・両眼視・外斜視・内斜視)の簡易検査:近くと遠くを交互に見てもらってピントが合うか?まばたきは正常か?
眼表面症状の確認:ドライアイの有無。異物感。光過敏。涙目などがないか?
これらを包括的に評価することで、眼関連起因の可能性を把握できます。
そして専門医の協力が必要なのか?なども踏まえ、自身の施術と同時に行う必要のある事柄についても助言をしやすくなります。
どうしても自分の提供できるサービス内で症状の全てに対応しようとすると限界がありますが、他の専門家への紹介なども含めて施術を考える事ができれば、よりお客様の需要に真摯に応えることができるはずです。
介入・アプローチ
整体などの手技療法でのアプローチでは頭部や頚部、肩部、肩甲帯周辺の筋膜へのアプローチが考えられます。
それによって頭部への虚血を解消し頭痛の緩和につなげることができます。
また頚椎から頭部に走る神経(大・小後頭神経)周囲のリリースや、咀嚼筋(側頭筋など)のリリースも頭痛には効果的なケースが多いです。
指導やアドバイスでは、スマホやPCとの距離、明るさ・反射などの調整などを指導を必ず行うようにしましょう。
「コンタクトレンズや眼鏡の度数が合っているか?」なども確認し、合っていないのであれば専門医にかかり調整を行うように促すことも大切です。
セルフケアでは目の運動を指導しましょう。
内容としては輻輳訓練(近見遠見交替)、サッカード訓練(視線移動)、追従運動訓練などがあります。
生活習慣の気をつける部分としては、ドライアイなどの眼表面ケアをお声がけしましょう。

まとめ
どうでしたでしょうか?
眼と頭痛の関係性は、視覚入力・眼運動・眼表面・神経血管系・筋膜・姿勢など複合的なシステムとして捉える必要があります。
臨床では、頭部に関係する筋や神経のリリースだけではなく、眼の状態や眼運動・視覚矯正介入についてもしっかりと触れてお話するようにしましょう。
対象者の頭痛への理解度と解像度が、症状の改善具合に大きく関係します。
今回ご紹介した眼と頭痛に関しての情報で、皆さんの臨床へ活用できる内容があると嬉しいです。