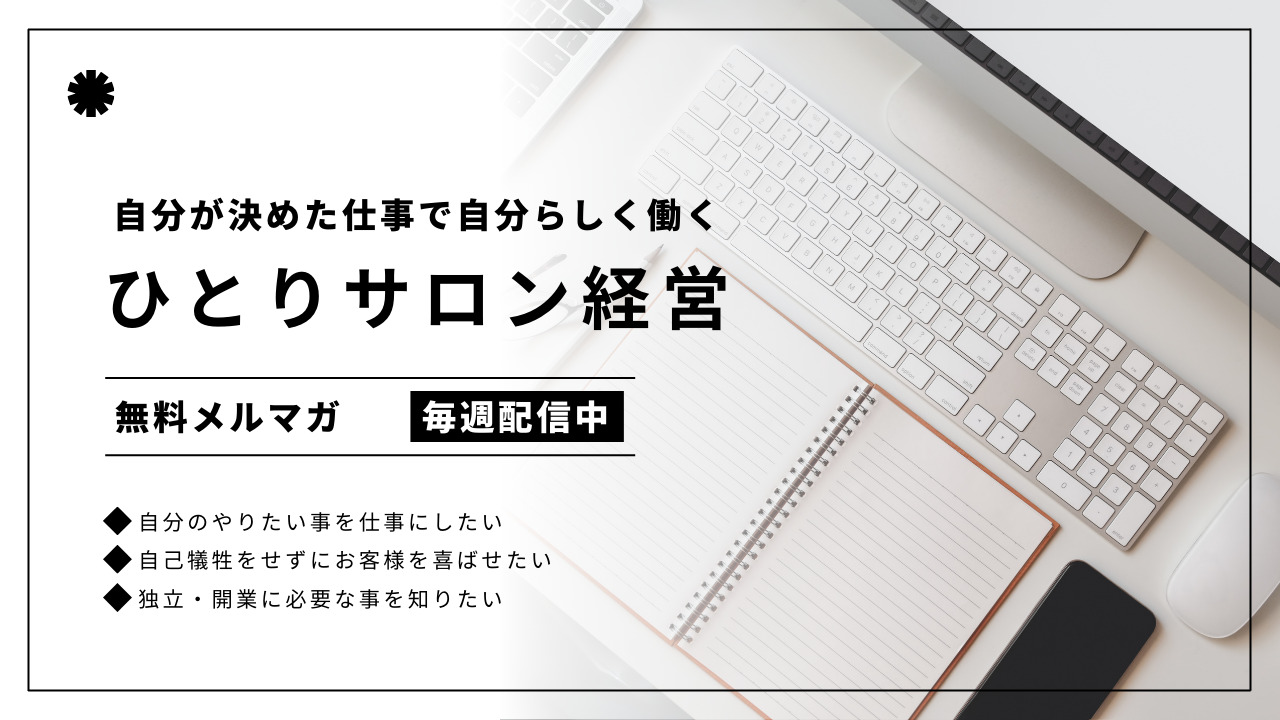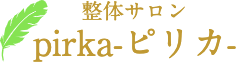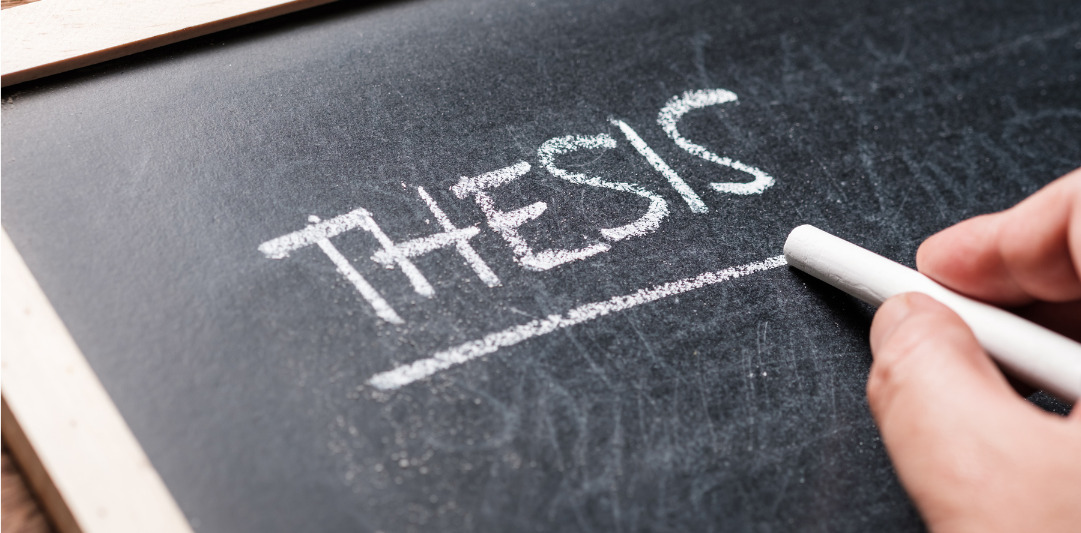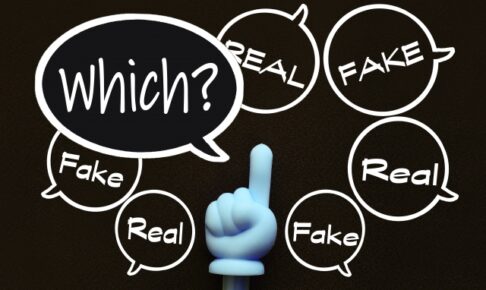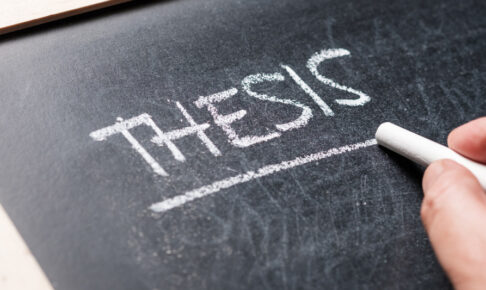こんにちは。整体サロンpirka-ピリカ-の山田です。
整体師、柔道整復師、理学療法士、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった、身体に関わる専門職にとって「科学的根拠に基づく判断」は避けて通れない課題です。
臨床現場において、新しい施術法やエクササイズ、指導方法などを取り入れる際に、その方法が本当に効果的であるかを判断する材料として「科学的論文」が用いられます。しかし論文の読み方を誤れば確証バイアスに陥り、自分に都合の良い解釈しかできなくなる危険があります。
今回の記事では、科学的論文の見方について、普段私自身が気をつけている事を含めて確証バイアスを避けるために必要な比較検討の視点を含めて解説していきます。
目次
科学的論文の位置づけ
科学的論文は、仮説を検証し、その結果を科学コミュニティに共有するための媒体です。論文を通じて得られる知見は、施術や運動療法の実践に大きな影響を与えます。しかし、論文が示す結果は「絶対的な真実」ではなく「一定の条件下で得られた傾向」にすぎません。
論文は更新され、反証され、比較されることで科学的知識が精緻化されていきます。
そのため、一つの論文結果だけを根拠に臨床判断を下すことは危険な事を必ず知っておきましょう。
例えば、ある施術方法について「効果がある」と結論づけた論文が存在しても、別の研究では「有意差がなかった」とされることもあります。この差異を理解するためには、論文を批判的に読み解く視点が求められます。
確証バイアスの罠
人は誰しも、自分の信念や経験を裏付ける情報に偏って目を向けがちです。これを「確証バイアス(confirmationbias)」と呼びます。
例えば「ストレッチは必ず腰痛に有効だ」と思い込んでいる人は、ストレッチの有効性を支持する論文ばかりを引用し、効果が限定的であることを示す論文を無視する傾向があります。
このような読み方は、科学的根拠に基づいた臨床判断をしていると思っていても、実は認知が歪んでいるケースがあります。
この確証バイアスを避けるには、賛成意見だけでなく反対意見も必ず探し、比較検討する姿勢を持ちましょう。
つまり、この施術法が「有効である根拠」と「有効でないとする根拠」を両方読み、そのうえで自分の臨床環境に最も適した判断を下す事が大切なのです。

論文を批判的に読むためのポイント
論文を読む際には、以下の観点から批判的に評価することが重要です。
研究デザイン
ランダム化比較試験(RCT)、システマティックレビュー、コホート研究、症例報告など、研究のデザインには階層性があります。
一般的に、システマティックレビューやRCTはエビデンスレベルが高く、症例報告や専門家の意見は低いとされます。しかし、これは「低いから読む価値がない」という意味ではなく、知見の強さや汎用性を判断するための基準として理解しておきましょう。
被験者の特性
研究に参加した被験者の年齢、性別、職業、健康状態などは結果に大きな影響を与えます。
例えば、若年のアスリートを対象とした研究結果を、高齢者の慢性腰痛患者にそのまま当てはめるのは適切ではありません。
論文を読む時には、「この論文の前提条件は何か?」を頭の中に入れた状態で読み進める事が重要です。
サンプルサイズ
被験者の人数が少ない研究は、結果が偶然に左右されやすくなります。少数例の結果は臨床に参考にはなりますが、一般化には注意が必要です。
測定方法
アウトカム(成果指標)が何であるかを確認することも重要です。疼痛スコア、筋力測定、可動域、QOL(生活の質)など、どの観点で効果を測定しているかによって、結論の解釈は変わってきます。
例えば「PS(ペインスケール)」であれば自覚的強度になるので客観的指標にするには心許ないです。
利益相反
研究者が施術法の開発者や器具の販売会社と関係している場合、結果にバイアスが生じる可能性があります。
利益相反の開示は重要なチェックポイントです。ポジショントークというものがありますが、研究者がどの立場から研究を行っているかによって結果に対しての解釈やデータの抽出方法が変わることは理解しておく必要があるでしょう。
解釈の例題
一つの論文結果を鵜呑みにするのではなく、複数の論文を比較することが重要です。以下に例題を挙げたいと思います。
Aら(2001)は、多裂筋の再教育が腰痛改善に有効であると報告しました。
Bら(2016)は、体幹安定化エクササイズと一般的な運動療法を比較したところ、大きな差は見られないと報告しました。
Cら(2016)は、慢性腰痛に対する運動療法のシステマティックレビューを行い、効果はあるがその大きさは中等度であると結論しました。
これらを総合的に見ると、「体幹トレーニングは腰痛改善に役立つ可能性はあるが、万能ではない」と解釈する事ができます。つまり、自分の臨床に導入する際は「体幹トレーニングを絶対視するのではなく、患者の背景や他の治療法と組み合わせて活用する」というスタンスが求められます。
まとめ
どうでしたでしょうか?
科学的な論文を読む時には知識だけではなく、総合的な知性が求められます。
私自身も論文を読みますが自分の推測に沿った論文をついつい選んで読みがちです。(気をつけなければ・・)
確かにマーケティング上では「断定をする」方が顧客にはウケが良いです。
明確かつ分かりやすく、0:100のキラーワードの方が記憶に残りますし人に刺さりやすいので。
ただし臨床に利用する時や応用する時、正確に論文の内容を理解する時には、可能な限り中庸的な視点を維持しつつ確証バイアスに陥らないように気を付けましょう。
身体に関わる専門職の方々の参考の一助になれば幸いです。