こんにちは。整体サロンpirka-ピリカ-の山田です。
遅発性筋痛(DOMS)は、一般的に激しい運動や慣れない動作を行った24〜72時間後にピークを迎える筋肉痛の事を指します。整体師、理学療法士、柔道整復師、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった身体に携わる専門家にとって、この現象はクライアントへの説明責任やケア戦略が大切です。
この記事では、DOMSの発生メカニズム、既存のエビデンスに基づいた回復促進法を整理しつつ、比較的視点を踏まえて考察してお伝えしていこうと思います。
整体師、柔道整復師、理学療法士、鍼灸師、セラピスト、トレーナーといった身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。
目次
DOMSの発生メカニズムと回復方法
DOMSの発生メカニズム
DOMSの原因については完全に解明されていませんが、多くの研究では筋線維損傷と炎症反応が主要因と考えられており、特にエキセントリック収縮(筋肉が伸ばされながら力を発揮する動作)が筋損傷を引き起こすことが知られています。
その結果、細胞内カルシウムの流入や炎症性サイトカインの分泌が起こり、痛覚受容器が刺激されることによってDOMSが起こるとされています。
科学的根拠に基づいた回復方法
(1)アクティブリカバリー(軽い運動)
軽度の有酸素運動やストレッチは、血流を増加させ老廃物の除去を促進するとされています。多くの研究論文で軽運動はDOMSの主観的な痛みを一時的に軽減する効果があると報告されています。
(2)冷却療法(アイシング)
アイスバスや局所冷却が炎症を抑え、筋痛を軽減する可能性が示されています。だたし、筋肥大や長期的な適応に対してはネガティブな影響を与える可能性も報告されており、短期的な疼痛緩和目的で用いるのが望ましいといえます。
(3)温熱療法
対象部位を温めることで血流改善を通じて回復や治癒を促進する効果が見込まれています。温熱療法がDOMSの痛みを緩和し筋機能を改善することを示しており、冷却と比較すると炎症抑制効果は弱いがリラクゼーション効果や疼痛耐容度の向上に寄与するとされます。
(4)マッサージ
マッサージは局所循環改善と神経生理学的な疼痛緩和効果が期待できる手技です。DOMSの回復方法は様々な研究がされていますが、マッサージが筋損傷後の痛みを有意に軽減し、筋機能の回復を促進する結果が出ているケースは多いです。整体師やセラピストにとっては実践的かつ効果的なアプローチだといえます。
(5)栄養補給(タンパク質や抗酸化物質)
筋損傷の修復にはアミノ酸供給が不可欠です。特に分岐鎖アミノ酸(BCAA)は筋損傷を軽減する可能性が示されています。また、ポリフェノールやビタミンC・Eといった抗酸化物質も炎症や酸化ストレス軽減に寄与する可能性があとされていますが、過剰摂取はトレーニング効果を阻害する恐れがあるため注意が必要です。
(6)ストレッチ
従来はDOMSの改善に有効とされてきたが、近年のシステマティックレビューでは効果が限定的であることが示唆されています(あまり効果はないのではないか?と言っている論文が多い印象)。ストレッチは柔軟性維持や心理的リラクゼーションに有用であるが、DOMS軽減には明確に効果があるとは言えない状況です。
※上記では効果があると考えられているアプローチについてまとめてご紹介しました。
ただし別の条件や対象者では再現できない可能性があるので鵜呑みにはしないように注意しましょう。

DOMSへの現場でのアプローチ考察
DOMSへの対応は「単一の方法で解決する」ものではなく、複数の方法を組み合わせて最適化する必要があります。
トレーニング直後にはアイシングで炎症を抑制
翌日以降は軽い有酸素運動や温熱療法で循環促進
並行してマッサージや適切な栄養補給を取り入れる
といったように、時間軸や目的に応じて施術や指導を組み合わせて提供するようにしましょう。
整体師やセラピストは施術ベースでの介入、理学療法士やトレーナーは運動療法・運動指導を組み合わせることでお客様や患者様のニーズに応えることができます。
また高齢者へのアプローチを考える時には代謝・筋力・消化能力の低下などを加味して、体に負担が少なく効果が出やすものを選択し提供するように心がけましょう。

まとめ
遅発性筋痛は運動適応の一部であり、完全に避けることは難しいものです。
しかし、科学的エビデンスを踏まえて冷却・温熱・マッサージ・栄養・軽運動といった複数の戦略を柔軟に組み合わせることで、痛みの軽減と機能回復を早めることが可能であると考えられています。
とても身近な反応の一つであるのでニーズも多く施術などを提供する機会も多いかと思います。
個々の状況に応じた最適なケアを提供してあなたのお客様に喜んでもらいましょう。
身体についての専門職の方々の臨床への一助になれば幸いです。
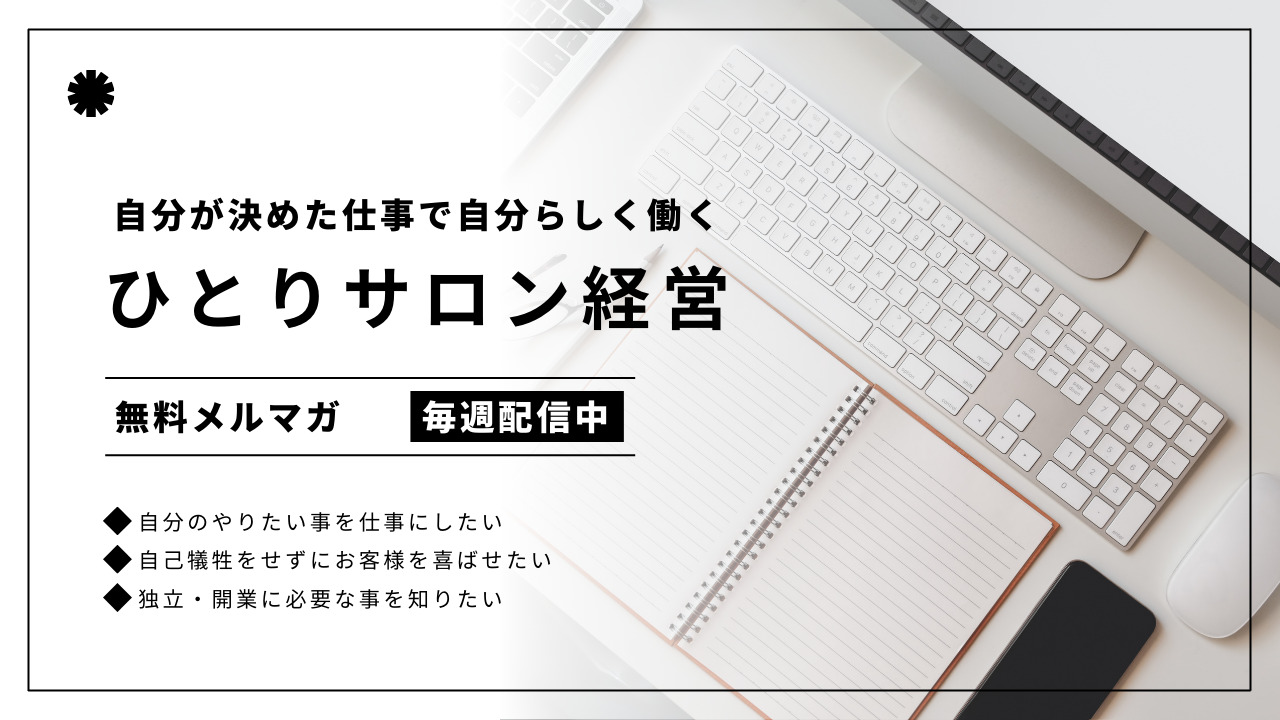
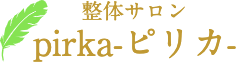

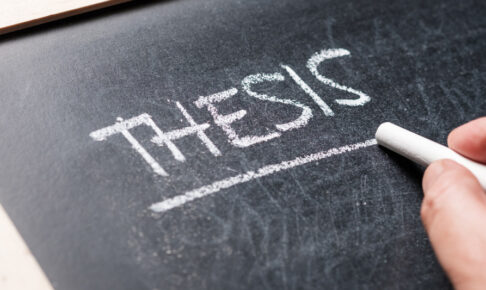
















そのため、臨床家やトレーナーは一つの手法に固執せず、複数のエビデンスを比較検討し、対象者の状態・目的・背景に合わせて使い分けることが重要です